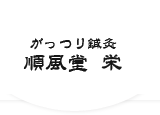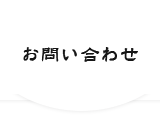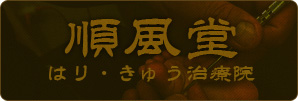健康診断の前日にしてはいけないことを改めて教えて!
新年度を迎えたということで検診などの機会が増えているみたいです。患者さんから健康診断の時の注意を聞かれて改めて調べてみました。
健康診断の前日にしてはいけないことを改めて教えて!
ここで言う「してはいけないこと」には、2つの意味が考えられます。1点目は、正確な診断を妨げてしまう不適切な行為。2点目は、バレたくない不都合をごまかすための隠ぺい行為です。その人にとっての「本当の姿」を映し出すためにも、改めて健康診断前日のタブー行為を知っておくべきでしょう。
飲食・薬など、胃袋へ納めるものの注意点
健康診断の前日の注意点というと、まずは食事制限が挙げられますか?
食事は、検査時間の「10時間前」から控えてください。検査が午前中なら、前日に早め夕食をとって、当日の朝食は抜きです。検査が夕方近くで10時間以上空けられるなら、当日の朝食をとっても大丈夫です。なお当院は、消化器系の検査を含まない場合に限り、食事制限をしていません。そのような方針を掲げている医院もありますので、ご注意ください。
水分はどうでしょうか?
胃のバリウム検査を含む場合は、食事と一緒で、「10時間前」から飲めません。口をうるおす程度なら構いませんが、ゴクゴク飲むと、きちんとした検査ができなくなります。暑い夏などは、検査日程を外すべきでしょう。また、飲み物の種類も「水」に限定されます。ジュースやお茶などは多くの胃液を出してしまうので、やはり、きちんとした検査ができなくなります。胃のバリウム検査をしない場合は、医院の指示に従ってください。
持病の薬や常用薬を飲んでいる人は?
検査直前の服用は止めていただきます。おそらく、予約時の用紙などに記載があるはずです。もちろん内服薬に限られ、塗り薬や点眼薬なら問題ありません。
健診前に、慌ててダイエットする人っていますよね?
正しい結果が出ない可能性があるので、直前のダイエットはやめましょう。仮によい結果が出たとしても、かえって疾患リスクを隠してしまいかねません。普段の生活を「採点」してもらうような意識で受診しましょう。頑張ってダイエットして、健診後のご褒美に「ドカ食い」するのは、最悪のパターンです。食事のほかに、前日の制限項目はありますか?
激しい運動は、肝機能の数値を高くすることがあります。筋肉を酷使するジム通いなどは、「1回お休み」していただきたいですね。
試合やウォーキングなどの運動も同様でしょうか?
程度にもよるので難しいですね。一般的に考えるなら、試合は「ダメそう」で、ウォーキングは「大丈夫そう」です。総じて、前日の激しい運動を控えてください。また、当日朝のウォーキングなどは、水分補給が絡んできますから、できれば見送るべきでしょう。
仕事はどうなのでしょう? 残業するとストレスが溜まりそうです。
ストレスの問題というより、無意識に食事や軽食をしてしまう可能性が怖いですね。帰宅後の食事時間まで考慮に入れて、うまくスケジュールを組み立てましょう。定時に帰れれば好ましいですが、そのまま徹夜でゲームなどをしてしまったら、意味がありません。おそらく、それが原因で血圧が上がるでしょうね。
タバコは確実に血圧を高めますよね?
医師としての回答は、「ぜひ、禁煙をしてください」です。しかし、個人的には、「検査前に吸う数本のタバコが何かしらの影響を与えることは少ない」と考えています。検査結果には、日頃の積み重ねが反映されるからです。
体重計と血圧計が健康をリードする
今度は、健診の結果を上げる方法について教えてください。
原則として、「短期間の取り組み」は意味がありません。かかりつけ医から言われている注意事項があったら、それを順守しましょう。また、生活習慣を根本から見直すとしたら、いわゆる「生活習慣病対策」が効果的です。
具体的には、どのような内容でしょうか?
適度な運動、栄養バランスのよい食事、目安として7時間以上の十分な睡眠、喫煙を控えることなどが該当します。
でも、どうしたって「言うは簡単、やるは困難」の面がありますよね?
体重計で毎日の体重を量ることと、血圧計で朝・昼・晩の数値を測定することは、案外、モチベーションの維持につながりますよ。数字の「見える化」が功を奏すのだと思います。目標値を置かずとも、日々、数字を見ているだけで「どうにかしよう」となるはずです。
最後に、読者へのメッセージがあれば。
医師から特段の注意を受けていることがあったら、きちんと守ってください。前回の健診に限らず、今度の健診についても同じです。どうしても忘れてしまう人は、目の付くところにメモしていただきたいですね。「明日の健診結果は気にしないでおこう」と思うことこそ、最もしてはいけないことでしょう。
日々の健康管理と健康のための自覚が重要ということですね。鍼灸治療も体調不良になる前から意識をしていると早く回復します。日々の意識改革が必要です。