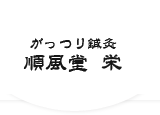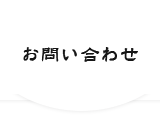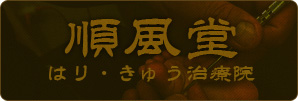花粉症の人がリンゴや桃で食物アレルギーに なぜ? 花粉とたんぱく質構造が似る意外な組み合わせに注意
「年がら年中、花粉症?何で?何に反応してるの?」という患者さんとの会話で見つけた記事です・
花粉症の人がリンゴや桃で食物アレルギーに なぜ? 花粉とたんぱく質構造が似る意外な組み合わせに注意
最近、子どもだけでなく大人にも増えているのが、花粉や天然ゴム、ペットなど私たちの身近に存在する食物以外のものが原因で起きる食物アレルギーです。今までその食物を食べてもなんともなかったのに、ある時期から急に、食べると唇が腫れる、のどがイガイガするなど、何らかの症状が出るようになったら要注意です。
時には、アナフィラキシーなどのショック症状を引き起こすこともあり、対応が遅れれば命に関わる食物アレルギー。その最新情報を食物以外が原因で起きる食物アレルギーを中心に取材しました。
食物以外のものがきっかけで起きる食物アレルギーで最も多いのは、花粉・食物アレルギー症候群です。これは、何らかの花粉症のある人が、関連する果物や野菜に対して症状が出るというものです。例えば、シラカバやハンノキなどカバノキ科の花粉症がある人たちがリンゴなどバラ科の果物を食べると、症状が出ることがあります。
■花粉症でリンゴや桃の食物アレルギー
「アレルギーを引き起こすたんぱく質の構造が、カバノキ科の花粉とバラ科の果物でとてもよく似ているため、これらの樹木の花粉症の患者さんたちがバラ科の果物を食べると、アレルギー反応が誘発されると考えられています」
「バラ科の果物にはリンゴや梨のほか、桃やサクランボ、イチゴなどのベリー系、ビワ、プラム、ウメなど、日本人が好んで食べるものが多いのです。必ずしもこれらの果物すべてで症状が出る、というわけではないのですが、リンゴ、桃で症状が出る場合が多いですね」
■生搾りのジュースに注意
症状としては、唇が腫れたり口の中がかゆくなったりのどがイガイガしたりといった、食べたものに触れる口の周りの症状が多く、これらの症状が出たら、それ以上は食べるのをやめることが大切です。
「一般的にはアナフィラキシーなどの強い症状は誘発されにくいですが、注意が必要なのは生搾りのジュースです。液体の場合は固形の果物より吸収が早いので、生搾りのジュースを大量に飲むと消化しきれないたんぱく質を吸収してしまい、症状が強く出ることがあります。一方、パッケージになって販売されているジュース類は加熱処理がされており、アレルギーを起こす力が弱まっているので大丈夫なことが多いです」
■ゴム手袋、クラゲ、猫、鳥…
このように、アレルギーを引き起こすたんぱく質の構造が似通っていることで、アレルギーの症状が起きることを交差反応(こうさはんのう)といい、花粉以外にもいろいろなもので起きることが、近年わかってきました。
花粉以外で多いのは、ゴム手袋などに使われる天然ゴム(ラテックス)が原因で起きるラテックスアレルギーです。普段仕事などで常にゴム手袋をするなどゴム製品に触れることが多い人が、バナナやアボカド、キウイフルーツ、栗などを食べるとアレルギー症状が出るようになる、というものです。
また最近明らかになったものに、納豆アレルギーがあります。クラゲに刺されたことがある人が、納豆を食べると症状が出る、というもので、クラゲと納豆のネバネバの成分が似通っていることで起きます。
このほか、猫を飼っている人が豚肉を食べると症状が出る(ポーク・キャット症候群)、鳥を飼っている人が卵や鶏肉を食べると症状が出る(バード・エッグ症候群)など、交差反応によるさまざまな食物アレルギーがあることがわかってきています。
「日本人の場合、花粉症の人がとても増えており、それに伴って交差反応の食物アレルギーも増えています。食物以外のアレルギーでも、タンパク質の構造が似た食べ物でアレルギーが起きることがある、ということを知り、症状が起きて怪しいなと思った食物は避ける。もし心配なら、ためらわずにアレルギーが専門の医師を受診してほしいと思います」
■次々にアレルギーを発症するアレルギーマーチ
子どもの場合、0歳時のアトピー性皮膚炎や食物アレルギーから始まり、2~3歳時には気管支ぜん息やアレルギー性鼻炎、学齢になると花粉症といったように、さまざまなアレルギーが起きる場合があります。アレルギーの病気が、まるで行進曲(マーチ)に乗ったように次々と発症することから、アレルギーマーチ、アトピックマーチなどと呼ばれます。
食物アレルギーには今のところ、これといった治療方法がないのが実情ですが、アレルギーマーチになるのを防ぐことは可能なのでしょうか。
「患者にはアレルギー体質が基盤にあるので、乳児期にアトピー性皮膚炎や食物アレルギーを発症した子どもは、アレルギーマーチを起こしやすい傾向があります。アレルギーになりやすい、なりにくい、というのは、アレルギー体質以外に成育環境が大きな要因となります。アレルギー体質は遺伝的に決まっているので変えられませんが、環境は変えることができます。例えば生活環境中のダニやホコリの除去など、できるだけ良い環境で過ごせるよう努力することが必要です。ただ、環境を整えればアレルギーマーチを食い止めたり発症を完全に防ぐことができるかというと、なかなか難しいですね」
「湿疹で肌のバリアが壊れていると、食物、ペット、ダニ、花粉などアレルギーの原因となるものが肌から侵入します。すると免疫機能が働いてからだの中でIgE抗体が作られ、次に原因物質が入ってきたとき、防御反応としてアレルギー症状が出てしまいます。まずは0歳のときにしっかりスキンケアをし、湿疹を治すことが非常に重要です」
食物アレルギーは近年、ナッツ類でアレルギーを起こす人が増えたり、食物以外のさまざまなものから食物アレルギーが引き起こされることがわかってきたりと情報が更新され、どんどん新しくなっています。最新の正しい情報をチェックしておくことが大切です。それらの情報はアレルギーのポータルサイトや、学会の一般向けホームページなどで確認することができます。
「食物アレルギーに限らずアレルギーを疑う症状では、自己判断をしないことと、正しい診断ができる医師に出会うことが何より重要です。最初に正しい診断を受け、自分の症状に最も合った治療を受けることで、その後の生活の質が全く変わります。そのためには、やはりアレルギーが専門の医師を探して受診することです。最寄りの病院にいなかったら、少し遠くても、がんばって専門の医師のいるところを訪ねていただければと思います」
アレルギーは怖いですよね・ 鍼灸治療は免疫力を効果的に上げることができます。