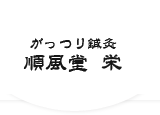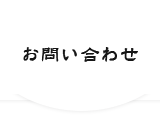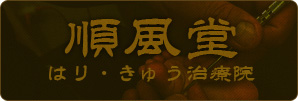10倍よくわかる!「健康診断結果」のトリセツ 人生を変える代表的8項目の「読み方」とは
患者さんに献身の結果を相談されます。わかりやすい記事を見つけましたので紹介しますね。
10倍よくわかる!「健康診断結果」のトリセツ 人生を変える代表的8項目の「読み方」とは
健康診断の結果はあなたの今の健康状態を知ることができる「情報の宝庫」です
■気になる「あの項目」の意味は?
健康診断は受けっぱなしにしないで、結果をしっかり見ることが大事です。
ところが多くの人は結果をよく見ずにしまいこんでしまいます。これは実にもったいない話です。健康診断の結果はあなたの今の健康状態を知ることができる「情報の宝庫」なのですから。
とはいえ「見方がよくわからない」という声があるのも事実でしょう。
そこで今回は「健康診断の結果の見方」について解説したいと思います。ページの関係ですべての項目を挙げるわけにいかないので「これだけはぜひ見てほしい」というポイントについて述べます。
まずは多くの方が気になるであろう「あの項目」から見ていきましょう。
血糖(空腹時血糖値)
この数値が高いと糖尿病のリスクが高まります。糖尿病になると脳卒中、心臓病を発症する危険性が高まります。また糖尿病の人はがんや認知症のリスクも増大します。
糖尿病患者は増加の一途をたどっています。予備軍も含めればその数は2000万人と言われています。糖尿病は一度なってしまうと一生の付き合いです。そうなる前に血糖値をしっかりコントロールすることが大事です。
血糖値を良好に保つことは、糖によって身体のタンパク質が変質する(糖化)を避けることになるので、老化予防に大きな意味を持ちます。
なお、血糖値については以前の記事「『血糖値が高い』と気にしている人の重大な盲点」も参考にしていただければと思います。
コレステロール
コレステロールは血中の脂質の一種です。コレステロールというと「動脈硬化になる」「高いとよくない」などといったネガティブなイメージを持たれることが多いのですが、実は体にとって非常に大事な働きをしています。
まずコレステロールは細胞膜を合成する材料です。またストレスに対抗するホルモンのコルチゾールや、男性ホルモン、女性ホルモンのもとにもなります。また胆汁酸の原料にもなり、脂質やビタミンの吸収を助けます。
エネルギー産生を支える抗酸化物質である「コエンザイムQ10」や免疫を支える「ビタミンD」は「コレステロールのきょうだい」のような物質です。
ですからコレステロールが低すぎるのも問題。不足すると元気がなくなったり、免疫力が落ちたりしてしまいます。
高めのコレステロールが気になる方は、コレステロールを胆汁に変換して排出する肝臓の機能を高めること(アルコールを控える、ビタミンCなど肝臓をサポートする栄養素を摂るなど)と、腸管に分泌された胆汁の再吸収を抑制するために、食物繊維の摂取を増やすことをお勧めします。
コレステロールは、糖質や脂質がエネルギーに変換される途中の物質「アセチルCoA」から合成され、タンパク質に包まれて血液中を運ばれます。
コレステロールが低い方は、糖質・脂質・タンパク質の三大栄養素の摂取や消化吸収がうまく行っていないのかもしれません。血糖値が安定するように上手に補食を摂ったり、タンパク質の消化が促進される様に胃腸のケアを心がけることをお勧めします。
■「疲れが取れない人」「朝起きられない人」はこの項目をチェック
MCV
血液検査の一項目で「赤血球の大きさ」を表す値です。このMCVは鉄が足りないと小さくなります。ヘモグロビンなどの値が基準値内であってもMCVが小さいと「鉄」が不足している可能性があります。
鉄がないと食べたものをエネルギーに変換することができず、「朝起きられない」「どうも元気が出ない」「頭痛」「肩こり」「冷え」「イライラが止まらない」などさまざまな困った症状が出ます。特に生理のある女性は鉄不足に陥りやすいので気を付けてください。
またこのMCVは数値が高すぎるのも問題です。ビタミンB12や葉酸が不足することで正常な赤血球がつくれず、「巨赤芽球性貧血」になっている可能性があるからです。
ちなみにビタミンB12や葉酸は血管にダメージを与える物質「ホモシステイン」を処理するために欠かせない栄養素でもあります。また、遺伝子の部品である核酸や、神経伝達物質の生成など体内で必要な様々な物質の合成に深くかかわっています。血管や脳をはじめ、全身の臓器を健康に保つためにも適切な補給がおすすめです。
■見逃しがちだけどチェックすべき項目
総蛋白
見逃してしまいがちですが、ぜひチェックしてほしい項目です。
十分なタンパク質を摂っているかどうかを知る手掛かりとなります。これも『サプリメントの正体』で強調したことですが、タンパク質は体の土台を支えるもの。不足するとさまざまな不調の原因になります。
総蛋白が不足している場合は食生活のバランスを見直しましょう。
またタンパク質をしっかり取っていても胃腸の機能が落ちていて、しっかり消化吸収できない場合もあります。その場合は、胃腸の機能低下の原因を把握するために、医療機関に相談することをお勧めします。
中性脂肪
中性脂肪もコレステロールと同じ、血中に含まれる脂質のことです。中性脂肪は私たちが活動するためのエネルギー源となりますが、摂り過ぎた分は皮下脂肪や内臓脂肪として蓄えられます。
中性脂肪は肥満の指標でもあるので、多くの方が気にされていると思います。しかしこれもまた高すぎるだけでなく、低すぎるのも問題です。ダイエットなどで過度の食事制限をしていたり、脂質を過剰にカットするなど、偏った食生活をしたりすると低くなります。
中性脂肪が低いとエネルギーが産生できず、疲れやすくなったり、寝ても回復できなかったりします。また冷えや免疫力低下、肌荒れなどの原因にもなります。まずは食事の見直しをすることが大事です。
■「生活習慣病のサイン」を読み取る
γ-GTP
お酒をよく飲む人、肝機能を気にする人にとっては気になるγ-GTP。肝臓の解毒作用に関わる酵素です。
この値が高いと、体に毒物が入っている、解毒が滞っているというサイン。多くの場合はお酒の飲み過ぎや煙草が原因ですが、それ以外にも毒物の存在があるかもしれないので、生活環境の見直しのきっかけに使えます。
逆に低すぎる場合は、タンパク質の摂取不足や消化吸収の問題を示している可能性があります。
ALT、AST
肝機能というとγ―GTPというイメージがあるかもしれませんが、ALT(GPT)、AST(GOT)にも留意が必要です。
ALT、ASTは肝臓で働く酵素ですが、肝臓の細胞が壊れると血中に流れ出ます。つまりこれらの数値が高いと肝臓に炎症が起こっている可能性があります。
肝機能が低下すると、タンパク質の合成や、血糖値の安定がうまくいかなくなり、疲れやすくなり、仕事のパフォーマンスも落ちてしまいます。肝臓は異常があっても自覚症状が出にくい臓器。まずはこれらの数値をよく見ましょう。
逆にこれらの数値が低い場合は、タンパク質やビタミンB6の摂取不足を示している可能性があります。
尿酸
尿酸値が高すぎると「痛風」になることはよく知られていると思います。
コレステロールと同じように「体に悪いもの」と思われていることが多いのですが、尿酸も体内において老化を促進する活性酸素を除去する働きをしてくれています。体内で最も多い抗酸化物質なのです。
ですから低すぎるのも問題です。尿酸値が低い人は、ビタミンCやビタミンEなどの抗酸化栄養素の補給を心がけてください。
■健康診断を軽視するとどうなるか
いかがでしたか?
健康診断に登場する検査項目は、私たちの体の状況を教えてくれるありがたい数値です。
車の運転をする際には、速度や冷却水の温度、バッテリーの状況、ガソリンの残量などをチェックすると思います。これらをまったく見もしないで運転するなんておそろしくてできません。
それと同じように、私たちも健康に幸せに生きていくためには、自分の体の状況を把握して、必要なメンテナンス(栄養の補給や運動、休養など)をする必要があるのです。
ぜひこの機会に最近受けた健診の結果をもう一度見直す、あるいは今後の健康診断の結果を注意深くチェックしていただきたいと思います。
自分自身を知ることは大事ですよね。