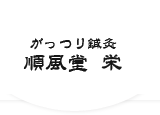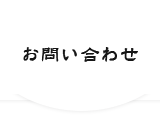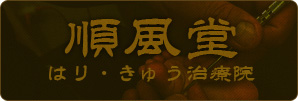睡眠不足にならないポイントは?万病のもと「睡眠負債」に注意しよう【専門家が解説】
カテゴリー:院長スケジュール2022年08月18日(木)
寝た気がしない。目が覚めてしまうという患者さんとの会話で見つけた記事です。
睡眠不足にならないポイントは?万病のもと「睡眠負債」に注意しよう【専門家が解説】
本当は怖い睡眠不足!あなたは大丈夫?睡眠負債に注意
睡眠不足は眠気や倦怠感、頭痛などを引き起こします。寝不足が慢性化すると「睡眠負債」が起こり、身体的な不調や精神的な不調の大きな原因に。健康に及ぼす悪影響や病気のリスク、睡眠不足にならないためのポイントを解説します。
睡眠不足ってどんな状態?
睡眠不足は「寝不足」とも呼ばれ、睡眠時間が十分ではなく、日中に眠気や倦怠感、頭痛などが起こる状態のことを指します。
厚生労働省が発表した「令和元年 国民健康・栄養調査の結果」によれば、男性の37.5%、女性では40.6%の人が1日の平均睡眠時間が6時間未満という結果が出ています。中でも、女性の40~50代では4割を超える人が睡眠時間が6時間未満ということがわかったのです。
「睡眠全体の質に満足できなかった」人は男性が21.6%、女性が22.0%。「日中、眠気を感じた」人は男性が32.3%、女性が36.9%と、十分な睡眠が取れていない人や、睡眠に対して不満を持っている人は少なくありません。
睡眠には「疲労回復」「記憶の整理」「傷ついた細胞の修復や体の成長を促す」という大切な役割があり、不足するとさまざまな問題が生じます。
■睡眠不足が続くと「睡眠負債」が起こる
「睡眠負債」とは、日々の寝不足が借金のように積み重なった状態のこと。毎日1~2時間ほどのほんの少しの睡眠不足がじわじわ積み重なると、慢性的な睡眠不足となり、身体的な不調や精神的な不調が現れるようになります。
睡眠負債は、長期間続くほど心身に大きな影響を及ぼすため、注意が必要です。
数週間続いた場合……自律神経が乱れ、高血圧や不整脈につながる
数か月続いた場合……ホルモンバランスが乱れ、肥満や脂質異常、糖尿病につながる
数年続いた場合……精神神経系の異常につながり、抑うつ状態を引き起こしやすくなる
15年ほど続いた場合……脳内の老廃物といわれるアミロイドβなどが除去されにくくなり、認知機能の低下、アルツハイマー病を引き起こしやすくなる
眠気や倦怠感、頭痛なども睡眠不足のサインですが、その他にも以下のようなサインが見られることがあります。
■間食や夜食に甘いものが食べたくなる
寝不足によって脳の機能低下が起こると、満腹ホルモンが減少し、食欲増進ホルモンが増加します。そのため「朝昼晩の三食以外の間食や夜食で甘いものが食べたくなる」という症状が起こりやすい状態に。
糖分を取り過ぎると、メラトニン(質の良い睡眠を促す物質)の分泌の遅れを招くため、悪循環になってしまう可能性があります。
■氷や飴などをガリガリ噛む
寝不足になるとセロトニンが低下し、気分が不安定になりやすくなります。
噛むというリズム運動はセロトニンの分泌を促す効果があり、心のバランスを取るためや目を覚ますためなど、寝不足の症状をカバーするために無意識に氷や飴などをガリガリ噛んでしまう人もいます。
■その他のサイン
その他にも、寝不足になると以下のようなことが起こりやすくなります。
忘れっぽくなる
部屋やデスクが散らかりやすくなる
人や物などによくぶつかるようになる など
睡眠不足によって起こる症状
睡眠不足になると、以下のようにさまざまな症状が起こります。
ストレスが増える
イライラする、怒りっぽくなる(キレやすい)
倦怠感
頭痛
集中力や注意力が低下する
血圧が上がる
睡眠障害
ここからは、それぞれの症状について詳しく解説していきます。
■イライラする、怒りっぽくなる(キレやすい)
睡眠不足になると、些細なことでイライラしたり、怒りっぽくなったりします。いわゆる「キレやすい」という状態です。
睡眠不足によって交感神経が優位になると、アドレナリンが分泌されます。アドレナリンには攻撃性を増す作用もあるため、イライラしやすくなるのです。
■倦怠感
睡眠不足になって睡眠リズムが崩れると、メラトニンが減少して睡眠が浅くなり、なかなか寝付けないなどの症状が現れます。
すると、ホルモン分泌や体温調節がうまくいかなくなり、疲労が十分に回復せず、倦怠感となって現れるようになります。
■頭痛
睡眠不足になると、脳の酸素欠乏状態が続き、頭の血管の収縮や筋肉が過剰に緊張することで、頭痛が引き起こされます。
■集中力や注意力が低下する
寝不足になると、脳が十分に働くことができなくなり、集中力や注意力、判断力、記憶力などの低下が起こります。
寝不足は、勉強や仕事での思わぬミスや事故につながる可能性も。また、意欲低下が見られることもあるようです。
■血圧が上がる
睡眠不足によって交感神経が優位になるとアドレナリンが分泌されますが、アドレナリンには血圧を上昇させる作用があります。
寝不足が続くと、アドレナリンなどのホルモンの影響によって、夜も血圧が高くなる可能性があるでしょう。血圧が高い状態が続くと、循環器系疾患のリスクが高まります。
■ストレスが増える
睡眠中は、脳内にたまった情報の整理も行います。そのため、蓄積されたストレスも睡眠によって減少する仕組みです。しかし、睡眠不足になると、情報整理が十分行われなくなり、ストレスがたまったままになってしまいます。
また、睡眠不足が続くこと自体もストレスになります。ストレスの増加によって、睡眠障害を引き起こしてしまうこともあるため、注意が必要です。
■睡眠障害
睡眠障害とは、睡眠に関連する多種多様な病気の総称です。睡眠不足症候群、入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害、特発性過眠症、ナルコレプシー、睡眠時無呼吸症候群など、さまざまな疾患があります。
たとえば睡眠不足症候群は、慢性的な睡眠不足によって、日中に過眠(日中、目覚めていられないような病的な眠気)が起こる状態を指します。睡眠不足症候群の人は、平日は3~4時間睡眠、週末に10時間以上眠るなどの生活を繰り返している人が多いです。
睡眠不足になると、このような睡眠障害を引き起こしやすくなるため、注意しましょう。
ここからは、睡眠不足が与える影響やリスクについて解説します。
■免疫力の低下
ウイルスや細菌に対する免疫力は、睡眠中に維持や強化が行われます。そのため、睡眠不足は免疫力の低下を引き起こします。
睡眠時間が5時間未満の人は、8時間睡眠の人と比較すると、風邪をこじらせて肺炎になるリスクが1.4倍ともいわれており、健康に悪い影響があります。
■生活習慣病やさまざまな病気のリスク上昇
睡眠は、生活習慣病とも深い関係があることが知られています。質の悪い睡眠は、高血圧、糖尿病や狭心症、心筋梗塞、脂質異常症などの生活習慣病にかかるリスクを高める原因となるのです。
その他、うつ病や認知症などのリスクを高める要因でもあります。
■肥満につながる
睡眠不足になると、グレリン(食欲を刺激するホルモン)の分泌量が増加し、レプチン(満腹感を与えるホルモン)の分泌量が減少します。
食事をしてもなかなか満腹感を得られなくなることで、食べ過ぎてしまいやすくなり、肥満につながります。そして、肥満になると、生活習慣病のリスクが高まることに。
薬物治療をしても生活習慣病がなかなか改善しない患者さんの中には、睡眠に問題を抱えている人も多いと考えられています。
■体臭が強くなる
睡眠不足や偏った食生活などの不規則な生活は、皮脂の過剰分泌につながり、体臭が出やすくなります。また、生活習慣が乱れると汗に悪臭の原因になるアンモニアや乳酸などが高濃度で含まれるようになり、体臭が強くなることも。
寝不足になるとストレスも増加しますが、ストレスも体臭をきつくする原因です。体臭が気になってきたという人は、睡眠不足を改善することで症状が緩和される可能性もあるでしょう。
■短い睡眠時間は経済損失にもつながる
睡眠が大切だとはわかっていても忙しく、睡眠時間が短くなっている人も少なくないようです。しかし、睡眠不足になると、集中力や注意力、判断力、記憶力などが低下します。
アメリカのシンクタンク「ランド研究所」の調査研究によれば、日本人の睡眠不足を原因とした国家レベルの経済的損失は約15兆円ともいわれており、調査対象となった国のうちでも最大。
短い睡眠時間は個人だけではなく、国の経済にも影響を与えているのです。
■自分に合った十分な睡眠時間を取る
睡眠不足を防ぐためには、十分な睡眠時間を取ることが大切です。睡眠時間に絶対的な基準はなく、最適な睡眠時間は、体質や年齢などさまざまな要因によって個人差があります。
自分にとって十分な睡眠時間が取れているかどうかを判断するポイントは「日中に眠気でつらくならず、覚醒して過ごせるかどうか」。
睡眠時間は長過ぎても短過ぎても健康に悪影響を及ぼすため、自分に合った睡眠時間を取ることが大切です。
ベストな睡眠時間の目安は6~8時間前後といわれています。しかし、睡眠時間は加齢によって短くなるもの。これは年を重ねれば誰にでも起こる可能性がある自然な変化であるため、無理に若い頃のようにたくさん寝ようとせず、今の自分に合った睡眠時間を取るといいでしょう。
■朝起きたら太陽の光を浴びる
睡眠リズムが崩れると、体内時計が狂ってしまい「なかなか寝付けない」「朝すっきり目覚められない」など、余計に睡眠不足になってしまいます。
朝起きてから太陽の光を浴びると、ずれてしまった体内時計をリセットできます。朝起きたらカーテンを開けるようにするといいでしょう。また、散歩やウォーキングなど軽い運動もおすすめです。
■カフェインの量を少なくする
コーヒーや紅茶、緑茶などに含まれるカフェインには強い覚醒効果があり、飲み過ぎると寝付きが悪くなり、睡眠不足を招く原因になります。
昼過ぎ~夕方頃にカフェインを摂取すると、夜に寝付きが悪くなるなど睡眠に影響する可能性があるため、摂取するタイミングや量に注意しましょう。
■睡眠の質を高める
睡眠は、量(睡眠時間)だけではなく、質も重要です。長く寝ても、疲労回復できていなければ意味がありません。睡眠の質を高めるためには、以下のポイントを意識するといいでしょう。
日中は散歩などで体を動かし、活動的に過ごす
短時間の昼寝を取り入れる
寝る前にぬるめのお風呂に入浴する
寝る前の激しい運動は避ける
寝る前にスマホやパソコンを使わない
寝ている間にスマホの通知音や着信音が鳴らないようにしておく など
睡眠不足は万病のもと!睡眠負債に注意しよう
睡眠不足が続くと、眠気、イライラ、倦怠感、頭痛、集中力や注意力の低下、ストレス増加、睡眠障害や生活習慣病などの病気のリスク上昇など、健康にさまざまな悪影響を与えます。
毎日1~2時間ほどの寝不足だったとしても「睡眠負債」として蓄積していき、健康に影響するため注意が必要です。日中に眠くならないよう、十分な睡眠を取るようにしましょう。
睡眠は大事ですよね。鍼灸治療は睡眠の質を改善します。